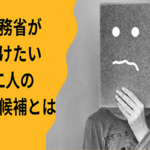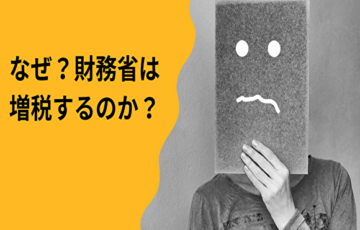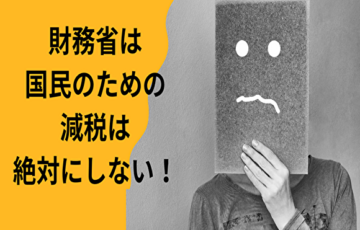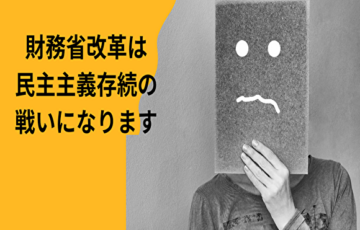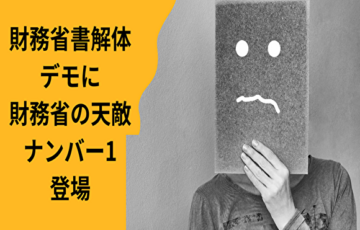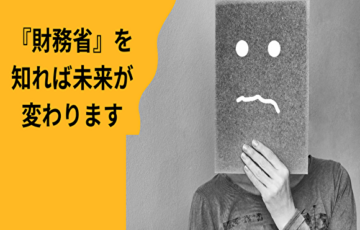財務省解体デモが全国に広がる中、財務省内部に潜む『反玉木』勢力の存在が明らかになりました。
玉木雄一郎国民民主党代表に対する「特別な感情」を持つ3人の財務官僚が、国民民主党の政策実現を阻止するために暗躍していたのです。
彼らは「玉木の思い通りにはさせない!」という個人的な感情から、石破総理への働きかけや日本維新の会との取引など、巧妙な分断工作を展開。「年収103万円の壁」引き上げを巡る攻防では、国民民主党が到底受け入れられない低水準案を提示し、交渉を実質的に決裂させました。
本記事では、財務省内の「反玉木」勢力の実態と、彼らが仕掛けた政治工作の全貌に迫り、今後の政局への影響を探る。
国民民主潰し!財務省内の『反玉木』勢力
玉木雄一郎氏は1993年に旧大蔵省(現財務省)に入省し、2005年に衆院選出馬のために退職するまでの12年間、財務官僚として勤務していました。
しかし、その在籍期間中は外務省や内閣府など他省庁への出向が多く、財務省内のエリートコースとされる主計局や主税局での勤務経験は限られており、このキャリアパスは、財務省内の有力OBからすれば「落第生」と見なされる要因となっています。
「近親憎悪」とも言われる感情的対立
財務省内には玉木氏に対して「特別な感情」や「激しい敵対心」を持つグループが存在しています。

この感情的対立は、単なる政策論争を超えた個人的な敵対関係に発展しており、財務省内の『反玉木』勢力の形成につながっているのです。
玉木氏の国民民主党が衆院選で4倍増の議席を獲得し、少数与党となった自公政権にとって無視できない存在となったことで、この対立はさらに先鋭化しているます。
財務省内に潜む「反玉木」中核人物3名の素顔
吉野裕一郎主計局次長:同期入省のエリート
吉野裕一郎主計局次長は、財務省内で「エース中のエース」と称される実力者です。
主計局は財務省の中核を担う部署であり、その次長という地位は将来の事務次官候補として最有力視される重要ポストです。
吉野氏は財務省内での影響力が非常に大きく、予算編成の実務を取り仕切る立場にあり、2025年度予算案の編成過程では、国民民主党の要求を抑制する一方で、日本維新の会との交渉を主導するなど、政治的な駆け引きにおいても手腕を発揮しています。
財務省の将来を担う中核人物として、省内での発言力も絶大であり、『反玉木』勢力の中心的存在となっています。
玉木雄一郎との同期入省が生む対抗意識
吉野氏が玉木氏に対して強い対抗意識を持つ背景には、両者が1993年に同期入省という関係性がある。
同じスタートラインから始まった二人だが、吉野氏は財務省内のエリートコースを歩み、主計局次長という要職に就いたのに対し、玉木氏は政治家に転身しました。
玉木氏が衆院選で大勝利を収め、政局の鍵を握る存在となったことで、吉野氏の対抗意識はさらに強まったと見られています。
「あいつだけには負けたくない」「あいつの思うようには進めさせたくない」という感情が、政策判断にも影響を与えているという指摘もあります。
同期入省という関係性が、単なる政策的対立を超えた個人的な対抗意識を生み出し、財務省内の『反玉木』工作の原動力となっているのです。
中島明弘首相秘書官:石破総理への影響力
中島明弘首相秘書官は、石破茂総理の側近として、政権の意思決定に大きな影響力を持つ立場にあります。
首相秘書官は総理大臣の日程調整や情報の整理だけでなく、政策判断に関する助言も行う重要なポストであり、総理の「耳」となる存在です。
石破総理は党内基盤が脆弱であり、少数与党という状況の中で政権運営を行っているため、側近からの助言に頼る部分が大きいようです。
中島氏は財務省から官邸に送り込まれた「刺客」として、財務省の意向を政権中枢に反映させる役割を担っており、玉木氏率いる国民民主党の政策要求を抑制する上で重要な役割を果たしているのです。
石破総理への働きかけの実態
中島氏は石破総理に密着し、「絶対に国民民主党の要求は飲んではいけない」と繰り返し進言していることが明らかになっています。
石破総理は党内基盤が弱く、前回の自民党総裁選では20人の推薦人すら集められず、岸田氏や武田亮太氏に頭を下げて何とか確保したという経緯があります。
そのため、リーダーシップを発揮しにくい状況にあり、中島氏のような側近の意見に左右されやすい立場にあります。
中島氏も玉木氏と同じ1993年入省組であり、同期入省の玉木氏に対する複雑な感情を持っているとされています。
この個人的な感情が、政策判断にも影響を与えている可能性があり、石破総理を通じて国民民主党の要求を抑制する方向に働いている。
一松潤大臣官房審議官:側近への接近戦略
一松潤大臣官房審議官は、石破内閣の経済再生担当大臣である赤沢亮政氏に接近し、強い影響力を行使しています。
赤沢大臣は石破総理の数少ない側近の一人であり、かつて財務省副大臣を務めた経験から財務省との関係が深いと言われています。
一松氏は1995年入省で、吉野次長の2期後輩にあたりますが、赤沢大臣の「知恵袋」として重用されています。
興味深いことに、赤沢大臣は経済再生担当大臣でありながら、内閣府よりも財務省に専用室を持ち、そこでの滞在時間の方が長いと言われており、これは一松氏の影響力の大きさを示すものであり、財務省の意向を政権中枢に伝える重要なパイプとなっているのです。
側近を通じた影響力行使の手法
一松氏は赤沢大臣に対して「絶対に国民民主党の要求を飲んではいけない」「年収の壁引き上げについては譲歩してはいけない」と繰り返し進言しています。
この意見は赤沢大臣を通じて石破総理にも伝わり、政権の意思決定に影響を与えています。
一松氏は財務省副大臣時代からの関係を活用し、赤沢大臣を「洗脳」するほどの影響力を持っているとされています。
この「側近への接近」という戦略は、直接総理に働きかける中島秘書官の手法と相まって、石破総理を「手足が縛られた状況」に追い込んでいます。
一松氏は吉野次長や中島秘書官と連携し、国民民主党の政策実現を阻止するための「反玉木」工作の一翼を担っているのです。
国民民主潰し財務省による「分断工作」の実態
日本維新の会を取り込む戦略
吉野次長による馬場前代表・遠藤元国対委員長への接近
財務省の吉野裕一郎主計局次長は、日本維新の会の馬場伸幸前代表と遠藤孝志元国会対策委員長に接近する。
吉野次長が日本維新の会の中でも特に「大阪系」と呼ばれる勢力に接近したのは、日本維新の会内で大きな影響力を持っているのが地元大阪の議員たちだからだとされています。
吉野次長は、日本維新の会の要求を一部受け入れることで予算案への賛成を取り付けようとする工作を行いました。
高校教育無償化と社会保険料負担軽減の分断戦略
日本維新の会は当初、「高校教育の無償化」と「社会保険料の負担軽減」という2つの政策をセットで実現することを目指していました。
特に社会保険料の負担軽減には4兆円の財政出動が必要とされていたのです。

これにより、日本維新の会の要求を分断し、財政出動を最小限に抑えつつ、予算案への賛成を取り付ける戦略が取られたのです。
国民民主党との交渉を妨害する手法
受け入れ困難な低水準案の提示
財務省は国民民主党との交渉において、最初から受け入れ困難な低水準の案を提示する戦術を取りました。

予算規模の大幅抑制による誘導
公明党の仲介で「160万円」という数字が浮上した後も、財務省は様々な条件を付けることで実質的な予算規模を大幅に抑制しました。
「年収200万円以下の人のみ適用」という条件や、段階的に控除額を下げていく仕組みを導入することで、総予算規模を「1兆2000億円程度」に抑え込みました。
これは国民民主党が求めていた「8兆円近い減税」からは大幅に下回るものであり、国民民主党が「到底飲めるわけではない」と判断せざるを得ない状況を作り出しnです。
こうした手法により、財務省は表面上は交渉に応じているように見せながらも、実質的には国民民主党の政策実現を阻止する工作を行った。
玉木雄一郎の反撃と今後の展望
参議院選挙に向けた対決姿勢
玉木雄一郎氏は、2025年度予算案をめぐる交渉が実質的に決裂したことを受け、7月の参議院選挙に照準を合わせ、「手取りを増やす夏」を掲げる戦略に転換しました。
国民民主党は4月2日に参議院選挙に向けた総合選挙対策本部を設置し、玉木氏自身が本部長に就任。
玉木氏は「候補者の擁立を含め、取り組みを加速していく」と述べ、改選4議席の4倍に当たる16議席獲得を目標に掲げています。
この目標設定は、前回の衆議院選挙で議席を4倍に増やした実績を踏まえたものであり、参議院選挙でも同様の躍進を目指す意欲を示している。
自民党・財務省との対決路線の意義
玉木氏が自民党・財務省との対決路線を強める背景には、予算案交渉の過程で明らかになった財務省の「反玉木」工作への対抗という側面があります。
玉木氏は「国民民主党との交渉はもう見込めない」と判断し、参議院選挙に向けて「徹底的に自民党と対決していく」姿勢を鮮明にしています。
この対決路線は、「対決より解決」を掲げてきた国民民主党の従来の路線からの転換を意味しますが、予算案交渉の過程で財務省が示した非妥協的な姿勢を考えると、「正しい選択」との見方もあります。
玉木氏は「下手に妥協することなく、7月の参議院選挙までには徹底的に自民党・財務省との対決姿勢を貫いていくべき」との認識を示しているのです。
【総括】国民民主潰し!財務省内に潜む3人の「反玉木」勢力と戦い
財務省内の「反玉木」勢力と国民民主党の対立は、単なる政策論争を超えた個人的な感情や組織的な抵抗が絡み合った複雑な構図を持っています。
玉木雄一郎氏と同期入省の吉野裕一郎主計局次長や中島明弘首相秘書官を中心とする財務省の中核人物たちは、「あいつだけには負けたくない」という感情を持ち、様々な工作を展開してきました。
2025年度予算案をめぐる攻防では、一松潤大臣官房審議官は石破総理や赤沢経済再生担当大臣への接近、日本維新の会の取り込み、国民民主党との交渉妨害など、多面的な戦略を駆使して国民民主党の政策実現を阻止しました。
「年収103万円の壁」の引き上げについては、当初から受け入れ困難な低水準の提案を行い、交渉の決裂を誘導する戦術が取られました。
こうした財務省の抵抗に対し、玉木氏は7月の参議院選挙に照準を合わせ、自民党・財務省との対決姿勢を強める方向に戦略を転換。「手取りを増やす夏」を掲げ、改選4議席の4倍となる16議席獲得を目指す姿勢を鮮明にしています。
「財務省解体デモ」に対しては、玉木氏は「役人たたき」には慎重な姿勢を示しつつも、その背景にある国民の不満や怒りについては政治が敏感に反応すべきだと主張しています。
物価高や税負担増加など、国民の「行き場のない怒り」が財務省という組織に向けられている現状を、政治の課題として受け止める姿勢を示しています。
今後の政局は、7月の参議院選挙に向けた与野党の攻防が焦点となります。
国民民主党が掲げる「手取りを増やす」政策が有権者の支持を集め、再び躍進するのか?複雑な政治情勢が展開されることになるでしょう。

財務省が避けたい2人の総理候補:玉木雄一郎と高市早苗の挑戦